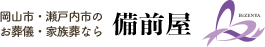日本人にとってお正月とは、新しい年神(歳神)様が訪れる大事な節目でした。年神様のトシとは稲のこと。年神様は稲作の神様であり、新しい年の豊作をもたらしてくれる神様でした。また、年神様は先祖の霊とも考えられています。12月13日のすす払いに始まるお正月の準備は、年神様を迎えるためのものです。松飾の松は、神様が降りて来る依代であり、神様を迎える目印して門や玄関に飾りますしめ縄を使ったしめ縄飾りも、神聖な空間を作り魔よけとする目的があります。各地方よってその飾り方は、多種多様ですし、現代ではさまざまな素材やアイデアを凝らしてアレンジされた飾りも少なくありません「鏡餅」は年神様の御供え物であり、年神様が……